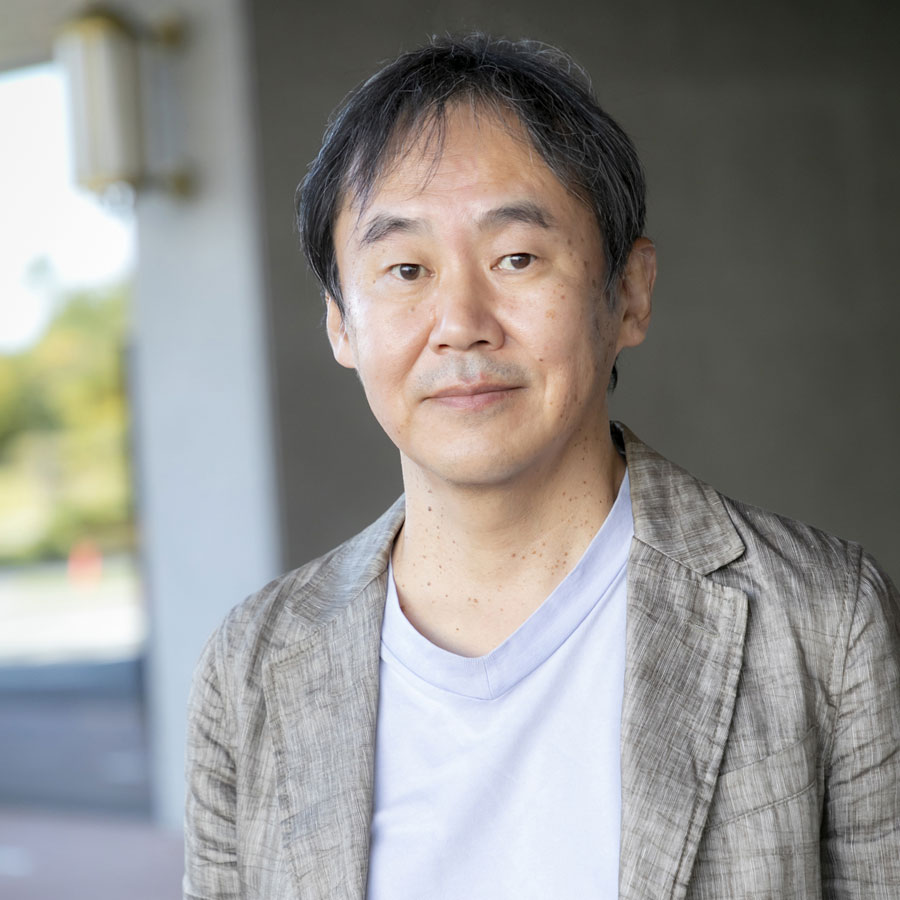ウラカン・シリーズのV10は忘れない! 自然吸気・純エンジン車のランボルギーニに感謝
公開 : 2023.02.25 18:35
ランボの60周年とともに、純エンジン車であるウラカン・シリーズも終わりを迎えます。自然吸気V10だけで走れるランボの新車、買える日は残り少ないです。
進化を続けたウラカンとV10
ランボルギーニは2022年をもって、内燃機関だけを積む車種の新車発表を終了し、今年からは電動化車両のみを送り出すと公表している。
日本では今週鈴鹿サーキットで発表されたオフロード志向のウラカン・ステラートが、最後の非電動ランボルギーニになるはずだ。

そんな中で行われた2023年のJAIA輸入車試乗会で、ウラカン・エボ・フルオ・カプセルに乗る機会を得た。
フルオ・カプセルは、外観は5タイプの蛍光カラーをメインとした2トーンとし、内装はブラックベースでアクセントカラー/トリムの選択肢を用意したもので、すでに完売となっている。
中身は従来のウラカン・エボと共通。つまり2014年にガヤルドの後継車として発表されたウラカンをベースに、2019年に登場した進化型だ。ボディはクーペとスパイダー、駆動方式はRWDとAWDがあり、試乗車はクーペAWDだった。
コクピット背後に縦置きされるのは、いまや希少となった大排気量自然吸気ユニット。5.2L V型10気筒は最高出力640ps/8000rpm、最大トルク61.2kg-m/6500rpmを発生し、7速DCTを介して4輪を駆動する。
640馬力を使い切れ LDVIとは
このユニットはかつてニュルブルクリンク北コースで量産車トップタイムをマークした限定車、ウラカン・ペルフォルマンテと同じものだ。
それ以上にウラカン・エボのトピックとなるのが、LDVI(Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata)の導入だろう。

簡単に言ってしまえば電脳化であるが、その中身は後輪操舵や4輪トルクベクタリングシステムなどを統合制御するうえに、ドライバーの気持ちを先読みして、それに見合った制御を入れるという先進的な内容だ。
全長4520mm、全幅1933mm、全高1165mmというサイズを持つボディもエボへの進化に伴い、エアロダイナミクス向上を施している。とはいえひさしぶりにウラカンに触れる人間にとっての第一印象は、まぎれもないランボルギーニというものだ。
それでいてマットブラックのサイドミラーやエアダム、リアスプリッターなどにボディ同色の挿し色を入れた姿は、ランボルギーニとしては落ち着いていて、個人的にはSTOやペルフォルマンテよりずっと受け入れやすい。
フルオ・カプセル 内装をチェック
コクピットはまず、イエローでステッチされたファイティングブルとウラカン・エボのロゴが目立つ。スタート&ストップボタンのカバーともども、フルオ・カプセルのパッケージに含まれているものだ。
インパネやセンターコンソールなどには、オプションで用意されるランボルギーニ独自開発の複合素材、 Forged Compositesが奢られている。

ヘキサゴンを多用したディテールとともに、フェラーリともマクラーレンとも異なる、ランボルギーニならではの世界観を、明確に表現していると感じた。
試乗車のシートは標準のコンフォートシートだったので、ヒップポイントはかなり低いものの、クッションはしっかり感じるし、ステアリングを含めて大幅な調節ができるので、理想のドライビングポジションが取れた。
イエローのカバーを開けてスタートスイッチを押すと、背後で轟音とともにV10が目覚める。
まずはトランスミッションをオート、ドライブはもっともおとなしいストラーダモードにして走り出すと、回転を低く抑えたまま、速度だけをスルスル上げていく。