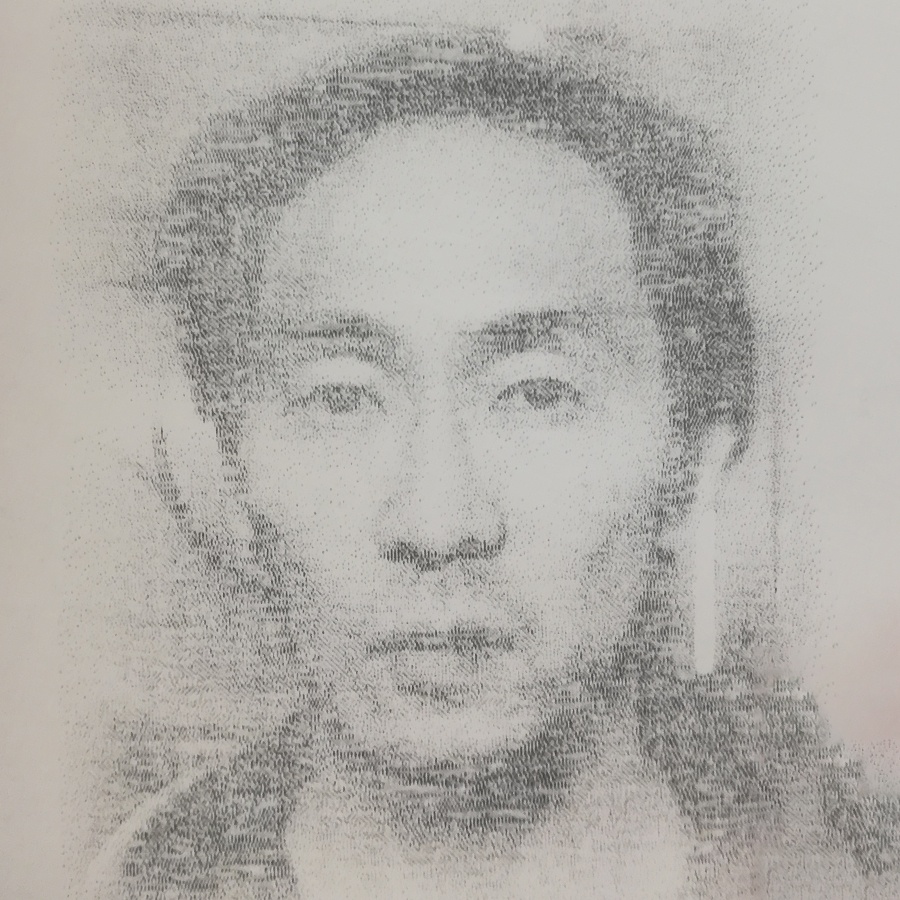【新車で買える1937年式!?】アルヴィスに、日本で試乗してみた 新・旧4.3リッター・バンデン・プラ・ツアラー
公開 : 2020.08.02 18:50 更新 : 2021.10.09 23:31
名にしおう戦前スーパーカー 驚くべき実力はどこに?
リアヒンジで天地の短いドアを開け、まずオリジナルの1937年式のシートに身体を預ける。
ツアラーの名の通り、後列シートをもつ4座の内装には薄いグレーのレザーが張られ、スポーティだが広々とした余裕をも感じさせる。

ステアリングホイール上には点火の進角調整レバーとチョークがあるが、ホットスタートである以上、いずれも不要。ダッシュボード中央のキースイッチで電源をONにすると、後ろから電磁ポンプのコッコッコという低くくぐもった音を、久しぶりに聞いた。
電源キーすぐ右のイグニッションボタンを押すとクランキングが始まり、ガスペダルを少し煽ると、4.3Lストレート6が目を覚ます。
正直、乗る前はケータハムやモーガン的な「プリミティブな楽しさ」を想像して高を括っていたので、総じて恐ろしく洗練されたフィールに舌を巻いた。
まず重たいとはいえ、発進時のクラッチ操作にコツらしいコツは要らない。
Hパターンの4速MTの感触こそ、固くて最初は難儀したが、ニュートラル位置から叩きこむのではなく、遊びのないゲートの入口をシフトレバーで探り当てた後、ゴリッと押し込むまたは引き込む、そうやってひと呼吸おく感覚に慣れると、じつは扱い易いトランスミッションであることに気づく。
元よりフルシンクロだがダブルクラッチを使うと素晴らしく素直に入ってくれる。大した剛性感だし、そもそもエンジンを楽しむのにシフトフィールの頼もしさは大前提であることを再認識させてくれた。
ビッグボアの直6 滑らかな回転フィールに違い
躾の行き届いたソリッドな感覚は、エンジンの回転フィールやシャシーの剛性感にも及ぶ。
ガスペダルを踏み込むと大きなボア特有の、ツブの揃った燃焼フィールが滑らかに、しかし太いトルクを発しながら、レブカウンターの針が力強く昇りつめていく。

3500rpmまでのグライド感はクルーズ向きだが、そこを越えるとエグゾーストノートは一段と、唸りのピッチとトーンを上げて野性味を増す。お手本のようなストレート6だ。
3m超えのホイールベースにウォームローラーの細身ステアリングは、確かにタイトベンドでは重労働で、右周りの袖ケ浦ゆえ翌々日、左上半身だけが筋肉痛になった。
だが戦前車とはいえ高性能なエンジンから絞り出される、経験したことのないスピード感は、まさしくスーパーカーだ。
このオリジナルのフィールが身体に染みついている内に、2020年メイドの1937年式4.3Lバンデン・プラ・ツアラーに乗り替えた。ドアハンドルを握った瞬間、そのエッジの立ち具合からして新しいクルマだ。
今の法規制に対応する以上、3連SUキャブに代わってインジェクション採用し、進角調整もチョークレバーも見当たらないが、電源キーを捻ってイグニッションを押すエンジンスタートの儀式は同様だ。
トランスミッションもトレメック社製の6速MTで、シフトレバーの遊びの無さや剛性感ではオリジナルと比べるべくもないものの、ずっと現代的なシフトフィールゆえ、戸惑いはない。